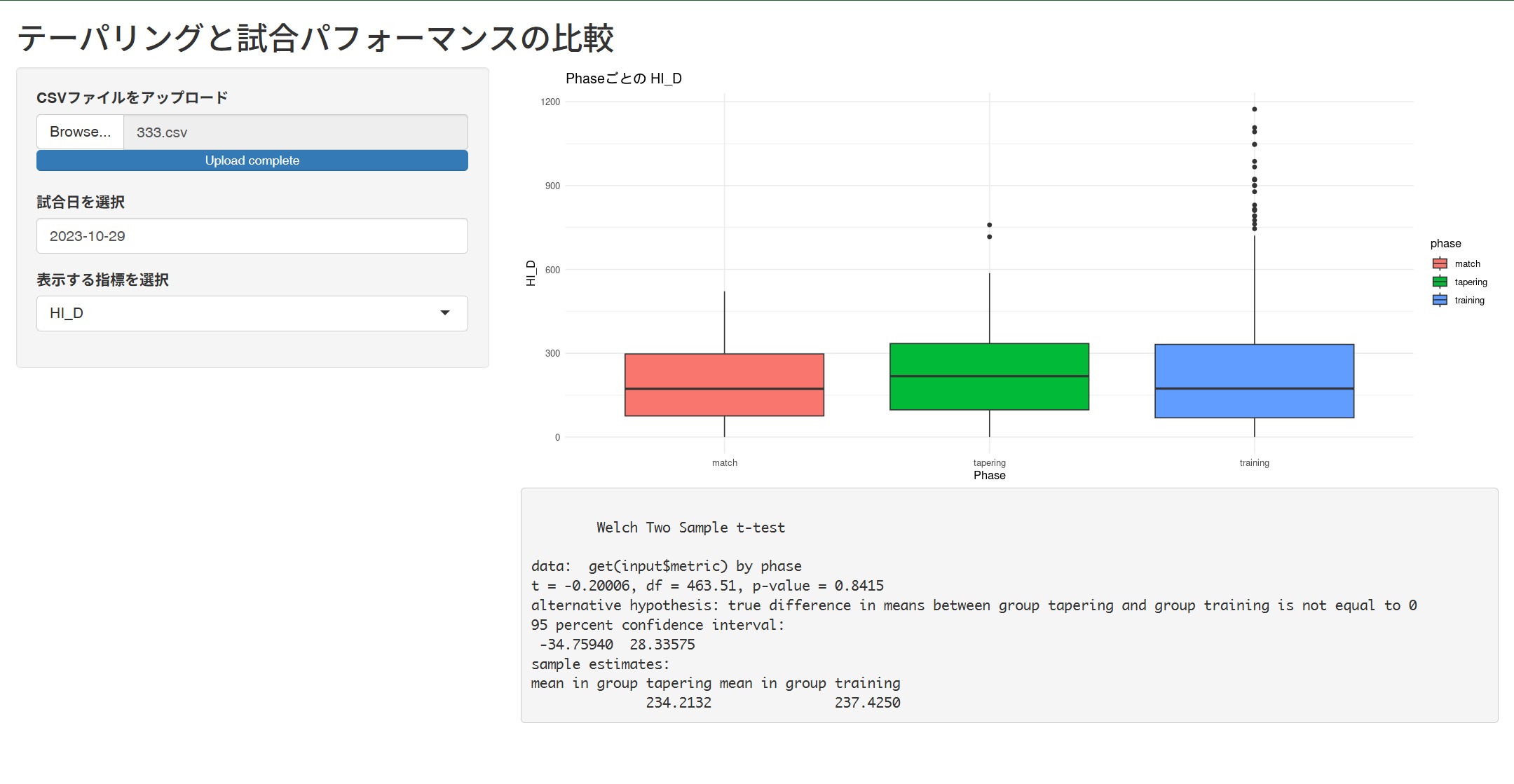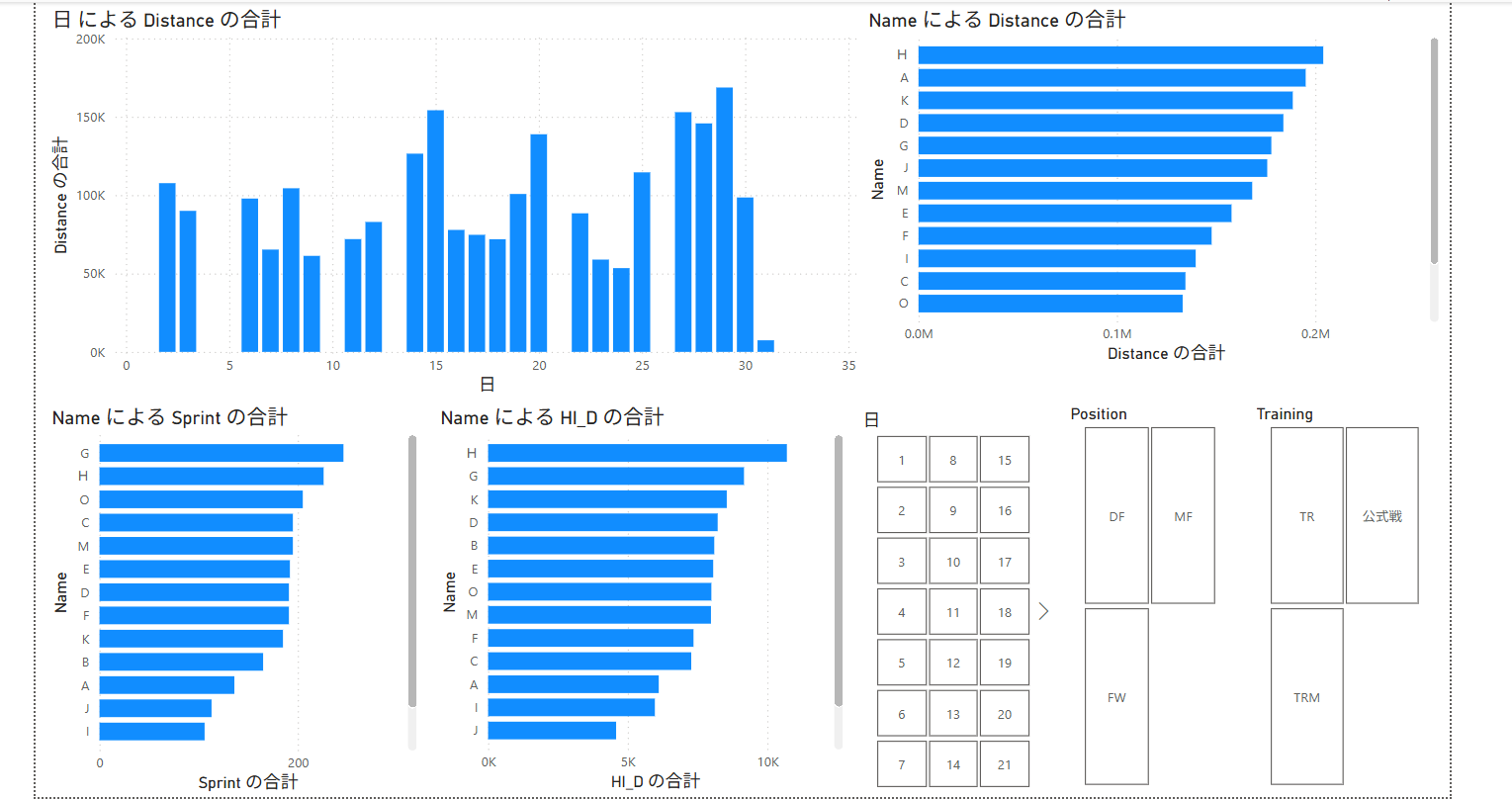サッカーにおける試合直前の調整方法論文5選について
deda
今回のブログでは、試合直前の調整方法(テーパリング)について、近年の研究における論文をご紹介したいと思います。
試合直前の調整は、難しいと思います。しかし、試合内容との相関もいくつか報告されています。
これは、2025年4月の論文です。サッカーにおいてランニングをKPIにするのは辞めようという面白い論文です。
研究の目的
- 試合中のランニング活動(例:走行距離)をKPIとする妥当性に疑問を呈し、
- 「選手の準備状態(フィットネス・フレッシュネス)」と「試合結果」の関係を分析。
主な結果
| 試合結果の比較 | 主な影響要因 | 備考 |
|---|---|---|
| 引き分け vs 敗戦 | ランニング量(z-TD)が多いほど引き分けの可能性 ↑ | OR = 1.99, p < 0.001 |
| 勝利 vs 敗戦/引分 | z-FR×z-FI×z-TD の3要素の交互作用が有意 | 高フィットネス・高フレッシュネス・低走行距離で勝率↑ |
| ランニング量が多い | 勝利の可能性は むしろ減少 | OR = 0.47, p < 0.001(勝 vs 引分) |
・総走行距離は、勝敗とは関係なかった。
・総走行距離は、結果であって原因ではない。
〇高フィットネス×高フレッシュネス×低走行距離 = 勝率↑/TDが高いと勝率↓
これから、言えることは勝つためにはフレッシュな状態で試合に臨む必要があるという事です。
これは、プロサッカーチームにおける**試合結果(勝敗引き分け)が、翌週のトレーニング負荷(外的・内的)**にどのように影響するかを、**フルシーズン(45週)**にわたって調査した論文です。
主な結果
- 勝利の翌週は、他の結果よりもトレーニング負荷(sRPE-TL, 総走行距離)が有意に低下(P<.05)
- 敗北の翌週は、最も高いトレーニング負荷がかかっていた
- 引き分けの翌週は中間的な値
- この傾向は1試合週・2試合週いずれでも一貫
考察と実務的示唆
- コーチは無意識に、試合結果に応じてトレーニング計画を調整している可能性がある:
- 負けた後 → 強度アップ(再強化や修正の意図)
- 勝った後 → 強度ダウン(休養や維持重視)
プロサッカー選手において、1週間のトレーニング負荷(週次TL)と、週末の試合中の走行パフォーマンスとの関連性を分析しています。特に、どのようなトレーニング負荷が試合でのパフォーマンス最適化に寄与するかを探った論文です。
主な結果
1. 試合パフォーマンスと最も関連があった週次負荷
- 試合中のスプリント距離と最も相関が高かったのは:
→ 週中の高速走行距離(HSR) - 試合中の**加減速(ACC/DEC)**と相関があったのは:
→ 週のACC/DECの頻度と量 - 逆に、週の総走行距離やRPE合計(sRPE-TL)とは有意な関連なし
2. トレーニング負荷の「質」が重要
- 単に多く走るのではなく、試合に求められる走りの特性(例:加減速、スプリント)を週中に再現することが重要
考察と実務的示唆
- 量(走行距離など)よりも質(スプリントや加減速などの特性)が試合パフォーマンスに影響
- 試合でスプリントが多いポジション(例:ウイングやSB)では、週中にその刺激が不足すると試合でパフォーマンスが落ちる可能性
- 過不足なく再現する負荷設計が、パフォーマンス向上と怪我予防の鍵
プロサッカー選手において、**週次のトレーニング負荷(外的・内的)**が、試合での身体的および技術的パフォーマンスにどのような影響を与えるかを調査した論文です。
主な結果
| 関係性 | 結果の概要 |
|---|---|
| 週中のHSR・ACC量と試合中の走行パフォーマンス | 有意な正の相関あり(p < .05) |
| 週のトレーニング負荷が高すぎる場合(特に連戦) | 技術的パフォーマンス(パス成功率など)が低下傾向 |
| ポジション別ではMFが最もTLの影響を受けやすい | 距離・パス成功に影響が出やすい |
考察と結論
- 試合で求められるスプリント・加減速に対応するためには、週中にそれらの刺激を適度に与える必要がある
- 負荷の「質的内容」が重要であり、総距離やsRPEの合計だけでは不十分
- 技術パフォーマンス(判断、精度)を維持するには、過度な疲労を避ける必要がある → 量と質のバランスが重要
- テーパリング的な調整が必要(特に連戦時や重要試合前)
プロサッカー選手を対象とした週1回の試合と週2回の試合における負荷の違いについて調べた論文になります。
主な結果
- 週1試合(長い回復期間)
- MD-5から徐々に負荷を下げる典型的テーパリングパターン
- MD-1(試合前日)は外的負荷・内的負荷とも最小値
- 週2試合(短い回復期間)
- MD-3やMD-2にあたる日でも負荷が高く、回復期が短い
- 高速度走行距離や加減速回数は週1試合より全体的に減少
- 1試合あたりの外的負荷合計は週1試合より低いが、週全体では総負荷が高めになるケースあり
- 試合前日の負荷
- 週1試合:かなり低く設定(回復優先)
- 週2試合:やや高めになる傾向(時間的余裕なし)
結論・示唆
- 試合間隔が短い週は「完全回復前に次の試合」に入るため、負荷管理と回復計画の最適化が必要
- 週1試合 → テーパリング期間を確保できるため、試合前に大きく負荷を落とす設計が可能
- 週2試合 → 負荷の落とし幅が小さいため、非試合日のセッション強度をさらに工夫する必要
- GPSデータではHSDと加減速回数が試合間隔の違いを反映しやすい
スポンサーリンク
コピー
まとめ
これらが、試合結果と試合前の調整方法について発表されている論文です。比較的最近の論文が多いのが特徴です。言い換えれば、またこれからも発展する可能性がある分野でもあります。
スポンサーリンク
コピー